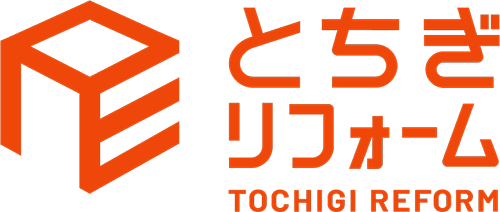耐震補強を木造住宅に住みながら行う方法|意味がない補強を避けるコツや費用相場を解説

木造住宅の耐震補強を検討中で、「自宅に住みながら効果的な耐震補強ができるのか?」とお考えの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、住みながらできる耐震補強の方法や費用相場、意味がない補強を避けるコツをわかりやすく解説します。
普段通りの生活を維持しながら地震に強い安心・安全な住まいを実現するため、ぜひ最後までご覧ください。
耐震補強には詳細な診断と計画が必要なため、まずは専門業者への相談をお勧めします。
住みながら地震に強い安心な住まいを実現したいという方は、とちぎリフォームへお問い合わせください。
Contents
木造住宅に住みながらできる耐震補強工事の方法

住みながらできる耐震補強工事の方法は主に以下の4つです。
- 壁補強工事を一部屋ずつ進める
- 接合部の金物補強工事
- 軽度な基礎補強工事
- 軽量な屋根材への変更工事
壁補強工事を一部屋ずつ工事を進める
木造住宅の耐震補強は、耐震性の高い壁を増やし、壁の配置バランスを改善することで、建物全体の耐震性能を高めます。
壁の耐震性を高めるためには、以下の補強方法があります。
| 補強方法 | 内容 |
|---|---|
| 筋交いの設置 | 柱と柱の間に斜めに補強材を入れる一般的な方法 |
| 構造用合板の取り付け | 壁面に合板を張り耐震性を向上 |
| 外壁の外側からの補強 | 外壁の外側に耐震フレームやブレース(※注)を取り付ける工法 |
(※注)ブレース:金属製の補強材で筋交いのように対角線上に部材を渡し、水平方向の強度を高める。
外壁の外側からの補強は、家具の移動や荷物の整理といった面倒な作業が発生せず、工期も短縮できます。
ただし、外側からの補強外壁を剥がさない補強の場合は、構造部分の劣化状況を詳しく確認できないため、不安を感じた場合には施工業者に相談しましょう。
接合部の補強工事
接合部の補強工事は、柱・梁・土台などの接合箇所に、専用の金物を取り付けて建物全体の強度を向上させます。
| 接合部 | 補強金物 |
|---|---|
| 柱と土台 | ・アンカーボルト ・ホールダウン金物 |
| 柱と梁 | ・羽子板ボルトによる引き止め |
| 柱と梁と筋交い 柱と土台と筋交い | ・筋交いプレート ・ひら金物 ・T型金物、V型金物 |
建築基準法が改正され2000年に、2階建て以下の建物にも金物による固定が義務化されました。
つまり、2000年以前に建築された2階以下の木造住宅は、金物が使用されていない場合があるため、接合部の補強工事により耐震性を向上できます。
軽度な基礎補強工事
建物の土台である基礎を補強し耐震性を高めます。
住みながら行える基礎補強工事は下記の通りです。
| 基礎補強 | 内容 |
|---|---|
| ひび割れ補修 | 基礎のひび割れに樹脂や繊維を注入して修復 |
| 基礎の打ち増し | 既存の基礎にコンクリートを追加して強度を向上 |
ただし、基礎全体の打ち直しや大規模な補強が必要な場合は、仮住まいが必要になります。
軽量な屋根材への変更工事
重い屋根材から軽量な屋根材に変更することで、地震時の住宅の揺れを軽減できます。
| 屋根材 | 特徴 |
|---|---|
| 化粧スレート | ・屋根材としてシェアが高く、コストパフォーマンスが良い |
| 軽量瓦 | ・瓦の趣を残しながら重量を軽減、和瓦からの変更がスムーズ |
| 金属屋根 | ・ガルバニウム鋼板など、屋根材として最も軽量 |
特に昔ながらの和瓦を使用している住宅では、屋根の重量が建物上部に集中しているため、地震時の揺れが大きくなりやすいです。
住みながらできない耐震補強工事

耐震補強工事の中でも、大規模な工事は住みながらの耐震補強工事は難しく、仮住まいへの移動が必要です。
住みながらの工事が難しい耐震補強は以下の3つです。
- 構造躯体の大幅な変更工事
- 基礎の全面的な打ち直し工事
- 複数箇所の同時施工による大規模工事
建物の骨格部分の大幅な変更工事
骨格部分の大幅な変更工事は建物の安全性が一時的に低下するため、お客様の安全確保の観点から仮住まいが必要です。
骨格部分の大幅な変更工事が必要となるのは、主に以下のケースです。
| 変更内容 | 工事内容 |
|---|---|
| 柱や梁の位置変更 | 建物の骨格を変更する大規模工事 |
| 耐力壁の大規模な移設 | 既存の壁を撤去して新たな位置に設置 |
| 構造計算に基づく柱の追加 | 建物バランスを根本的に見直す工事 |
基礎の全面的な打ち直し工事
住宅の基礎部分に以下のような損傷がある場合は、全面的な打ち直し工事が必要です。
| 基礎の状態 | 問題点 |
|---|---|
| 大規模なひび割れ | コンクリート基礎に構造的問題を引き起こす深刻な亀裂 |
| 無筋基礎の改修 | 鉄筋が入っていない古い基礎を鉄筋コンクリートに変更 |
| 地盤沈下による損傷 | 不同沈下で基礎に致命的な破損が発生 |
基礎の打ち直し工事はより確実に耐震性を改善できますが、住みながらの施工は現実的ではないため、仮住まいでの生活が必要となります。
複数箇所の同時施工による大規模工事
基礎補強・壁補強・屋根改修などの耐震補強と他のリフォームを併せて行う場合は、住みながらの工事はおすすめできません。
工事箇所が建物全体に及び、安全な生活スペースを確保することが困難なためです。
複数箇所の同時施工では工期が2ヶ月以上の長期間に及ぶケースも多く、ストレス軽減のためにも仮住まいへの移動がおすすめです。
意味がない耐震補強を避けるコツ

耐震補強が「意味がない」と言われる主な原因は、適切な診断を行わずに工事を実施したり、建物全体のバランスを考慮しない部分的な補強を行うことです。
正しい手順と方法で耐震補強をすれば、建物の耐震性を高めることができます。
耐震診断に基づく補強で確実な効果を実現
耐震補強工事で耐震性を向上させるには、必ず事前の耐震診断を実施することが重要です。
診断なしに行う工事では強化が必要な箇所を見逃したり、不要な箇所に過剰な補強をしてしまうリスクがあります。
適切な診断に基づかない補強工事は、費用をかけても期待される耐震性能の向上が得られず、結果として「意味がない」補強となってしまいます。
耐震診断で建物の補強が必要な箇所を明確化

耐震診断により建物の現状を正確に把握できたら、建物全体の構造バランスを考慮し、弱点部分を強化する補強計画を作成します。
診断段階で建物の弱点や補強が必要な箇所を明確にし、住みながら工事が可能かについても判断いたします。
耐震診断からの耐震補強工事は一般的に以下の流れで進められます。
| 耐震診断から耐震補強工事の流れ |
|---|
| 【現地調査・耐震診断】 建物の状況を調査し耐震性能を数値化 ↓ 【補強プランのご提案】 診断結果を基に具体的な工事内容と費用を決定 ↓ 【工事のお申込み・ご契約】 計画に従って実際の補強工事を実行 ↓ 【工事開始】 騒音やプライバシーに配慮した施工 ↓ 【工事完了】 お客さまに最終確認を行っていただき、お引き渡し |
木造住宅の耐震診断を検討中の方は、とちぎリフォームへお問い合わせください。
住みながら耐震補強する際の3つの注意点

住みながら耐震補強工事を行う場合、普段の生活への影響を最小限に抑える対策が必要です。
- 防音・防塵対策で快適性を確保する
- 荷物移動計画で生活スペースを維持する
- 工事範囲の確認でトラブルを防ぐ
事前の準備と適切な対策により、快適な生活を維持できます。
防音・防塵対策で快適性を確保する
耐震補強工事では、騒音や木くず・ホコリの発生は避けられないため対策が必要です。
住みながらできる防音・防塵対策は下記の通りです。
- 工事箇所をブルーシートで覆う
- 空気清浄機の設置(増設)
- 工事時間帯の外出
特に小さなお子様や高齢者がいる家庭、在宅ワークの方は、生活リズムに合わせた対策を考えておくことが大切です。
荷物移動計画で生活スペースを維持する
工事箇所の家具や荷物は必ず移動が必要になるため、事前に移動先と保管場所の確保が大切です。
▼荷物移動の準備
- 他の部屋へ移動可能な家具・荷物の選定
- 大型家具のレンタル倉庫一時利用の検討
- 不要な物を処分し荷物量を減らす
- 工事の進捗に合わせた段階的な移動計画の検討
工事を機に不要な物の処分を行い、生活に必要な最小限の荷物に整理することをおすすめします。
工事範囲の確認でトラブルを防ぐ
耐震補強の工事箇所や作業手順、工期を事前に把握しておくことで、予期しないトラブルを防げます。
▼事前確認が必要な項目
- どの部屋でいつ工事が行われるか
- 水道や電気の使用制限の有無
- 工事による生活への具体的な影響範囲
- 追加工事が発生する可能性と対応方法
工事内容によっては想定以上に生活への影響が大きい場合もあるため、不安や不明確な点は工事業者への事前確認が重要です。
木造住宅の耐震補強費用の相場

木造住宅の耐震補強費用は建物の階数や延べ床面積によって変動します。
平屋建てと2階建てでは工事規模や施工方法が異なるため、それぞれの費用相場を把握することが重要です。
木造平屋建ての場合
木造平屋建て住宅の耐震補強費用は100万円~150万円の範囲が最も多く、全体の約86%を占めています。
平屋建ては構造がシンプルで工事箇所が限定され以下の工事内容が中心となり、比較的費用を抑えやすい点が特徴です。
- 筋交いの設置や構造用合板の張り付け
- 接合部への金物取り付け
上記の工事に加えて基礎の状態や建物の劣化具合によっては、追加工事が必要です。
〈参考〉国土交通大臣指定耐震改修支援センター:耐震改修工事費の目安
※費用の目安は2020年公表当時の価格で昨今の物価高騰については考慮されていません。
木造2階建ての場合
木造2階建て住宅では平屋建てと同様に100万円~150万円の費用が最も多いものの、より幅広い価格帯に分散しています。
2階建ては平屋に比べて補強箇所が多く、1階と2階両方の構造バランスを考慮した工事が必要です。
- 1階部分の柱や壁、接合部の金物補強が重要
- 屋根材の軽量化
- 基礎や建物の状態応じた追加工事
平屋建てに比べて屋根の重さが耐震性に与える影響が大きくなるため、屋根材の軽量化も大切なポイントです。
〈参考〉国土交通大臣指定耐震改修支援センター:耐震改修工事費の目安
※費用の目安は2020年公表当時の価格で昨今の物価高騰については考慮されていません。
耐震補強工事を行う際の補助金制度

住みながら耐震補強工事を行う場合でも、各種補助金制度を活用できます。
自治体により上限額と条件が異なる
自治体の補助金制度は地域により異なり、上限額は数十万円から最大100万円まで幅があります。
耐震補強の補助金制度は住みながら工事を行うか仮住まいで行うかに関係なく、工事内容や金額、建物の条件で判断されます。
特に昭和56年5月以前に建築された木造住宅は、旧耐震基準で建てられているため、補助対象となる可能性が高いです。
自治体によって制度が異なるため、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。
栃木県の耐震補強工事の助成金
栃木県では住宅の耐震診断で基準より耐震性が低いと診断された場合、耐震補強工事の補助制度の適用となります。
栃木県で行われている住宅の耐震診断・耐震改修に対する助成事業は下記の通りです。
| 制度 | 内容 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断士派遣制度 | 耐震診断士を無料で派遣 | |
| 耐震補強工事の助成額 | 耐震補強工事にかかる費用の4/5 | 100万円 |
| ブロック塀補助 | 除去工事費の2/3 | 20万円 |
〈参考〉栃木県/住宅の耐震化について
また、耐震改修工事を実施した住宅には、優遇措置(固定資産税の減額など)も用意されています。
栃木県や各市についての詳しい補助金は、以下のページでも確認できます。
〈関連ページ〉
・栃木県の住宅リフォーム補助金一覧|対象工事や宇都宮市など主要市の内容も紹介
・小山市の住宅リフォームで活用できる補助金制度|申請方法や注意点も解説
・【2025年】佐野市のリフォーム補助金・助成金を解説|補助金活用のメリット、ポイントも紹介
・鹿沼市の住宅リフォームに活用できる補助金・助成金・減税制度|市・県・国への申請方法など簡単解説
補助金・助成金を活用した耐震補強を検討中の方は、とちぎリフォームへお問い合わせください。
まとめ|木造住宅の耐震補強は住みながら実現できる
住みながらできる木造住宅の耐震補強工事の方法から費用相場まで解説してきました。
壁補強・接合部補強・基礎補修・屋根軽量化の4つの工法は住みながら実施可能で、費用相場は100万円~150万円が最も多くなっています。
また、意味のない補強を避けるためにも、必ず耐震診断を実施し、建物全体のバランスを考慮した計画を立てることが大切です。
今回紹介した情報を参考に大切に住まわれているご自宅の耐震性能を高め、安心して暮らせる耐震補強工事の参考にしていただけると幸いです。